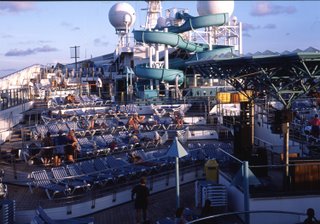シカゴのダウンタウンにアダムスという名の通りがある。有名なシカゴアートインスティチュート(シカゴ美術館)のある場所から始まって、西へと走っている通りだが、そのアダムスを入り口からほんの10数歩入ったところに、一つの標識がさりげなく建てられている。標識にはヒストリックロード・ルート66と記されている。あまり気づく人もいない標識だ。
ルート66……、別名オールド66。アメリカのマザーロード、またはアメリカのメインストリートと呼ばれる道。イリノイ州シカゴを出発し、ミズーリ州、カンザス州、オクラホマ州、ニューメキシコ州、テキサス州、アリゾナ州を走り抜け、カリフォルニア州サンタモニカビーチで終わる道。66の名は1926年に道路の設計者によって命名された。総距離数約2295マイル。
ナット・キング・コールによって歌われた『ゲット・ユア・キックス・オン・ルート66』(ボビー・トラップ作詞作曲)の大ヒットで世界的にその名を知られることになる(この歌はテレビ番組『ルート66』の主題歌となった)。
<西をへ旅するならハイウェイが最高さ>
という歌詞の『ゲット・ユア・キックス・オン・ルート66』は、いわばモータリーゼーションの象徴でもあった。アメリカのモータリーゼーションの発達ととともにルート66の名前はアメリカ全土に親しまれていったのである。
だが新しい高速道路が発達した現在、ルート66は分断され、あるいは新しい道路に吸収され、もはや昔日の姿を保ってはいない。アメリカのロードマップを広げてみるとわかるが、ほとんどの地図には66の文字が記されていない。モーターリーゼーションとともに発達したルート66は、皮肉なことにさらなるモータリーゼーションの発達とともにその生命を終えたのである。
ヒストリックロードとはいうものの、シカゴからロスまで走る高速道路にまるですがりつくかのようにして、かろうじて存在を保っているだけだ。
だがそれでもアメリカ人たちは愛情を込めて呼ぶ、……オールドルート66と。
私を乗せた車は一路西を目指した。そう私はルート66を辿っているのだ(ともに旅するのは写真家の小平尚典とレーサーの木内兼一郎である)。
ルート66をシカゴ郊外に行くに従って、風景は荒れたものとなっていった。私は忘れ去られ、置き去りにされた地域を走っているようだった。
シカゴは、開拓民たちがいわゆる西部へと進むための前進基地だった。66と名付けられたのは1927年だが、もちろんそれ以前から西へ向かうルートとして『道』自体は存在していたはずである。
ミシガン湖畔に建設された都市シカゴは、湖畔を渡る風が激しく吹き抜ける街だ。冬には零下三十度まで気温が下がることも珍しくない。そのシカゴから開拓民たちは、太陽を求めるように幌馬車で西へと向かっていったのだ。
私もまた彼らと同じように、シカゴから西を、明るい陽光の差すロサンゼルスを目指してみようと思った。
今日の予定はセントルイスまで。300マイル、480キロだ。セントルイスからミズーリ州となり、そしていわゆる西部が始まる。
(いわゆるというのは区分が時代や、分け方によって異なるからだ。現代ではイリノイ、ミズーリ、オクラホマ、中西部に属する)
幾つかの街を過ぎ、オールド66は高速道路55線に合流した。両側には畑の風景が一面に広がっている。イリノイ州はどこにいってもそうなのだが、目に入るのはトウモロコシと大豆と小麦の畑ばかりだ。これからロスに着くまで、特別な所に行かない限り、さして風景は変わることはないのだ……。
事実、イリノイ州、ミズーリ州、オクラホマ州と風景はほとんど変わることはなかった。多少森林が見えようと、畑の作物が変わろうが、数百マイルも走っていると同じようなものにしか見えない。広がるのは大平原ばかり。変わったことと言えば、最初の宿泊地であり、イリノイ州最後の街・リッチフィールドで宿泊した朝に大雪に降られたことくらいだ(私がルート66旅をしているのは春のことである)。
リッチフィールドにあるアリストンカフェの主人デニス爺さんは私をにこやかに迎えてくれた。この店はルート66ができる数年前、1924年創業だ。
「あんたは日本人だね。これからどこへ行くんだい」
「ルート66をLAまで行こうと思うんです」
「そいつは凄いじゃないか、一体今日で何泊目だね」
「ここが最初の宿泊地です」
「シカゴからここまで走ったのかい!! 無理をするんじゃない。まあこれから気を付けていきなよ」
アリストンカフェは観光名所だから、親切にしてくれるということはあるのだろうがそれでも旅人には温かい言葉はやはりうれしい。出逢いを期待して私はひたすら進む。
自然は変わらなくても人の姿は変わっていった。まず典型的なのは服装である。ミシシッピー河を越え西部に入ると、テンガロンハットにブルージーンズ、そしてブーツという画に描いたような西部の出で立ちの連中が目立って増えてくることだ。道路沿いにもジェシー・ジェイムズ(西部の義賊)やビリー・ザ・キッド(ご存知だろう。彼はニューメキシコ出身だ)といった西部の英雄の名前を記した看板が目立ち始めていた。
服装と同じように、西に行くにしたがってヨーロッパの影響の濃いちょっときどった東海岸的な人間も少なくなっていく。昼食や夕食に立ち寄るロードサイドのダイナーやカフェはたいてい一家で助け合うファミリービジネスだ。教養はないかもしれないが、素朴で働き者の男達や女達の姿がそこにはあった。
どれだけの日本人がオクラホマやその先のテキサスまでやってくるのかは知らない。不思議だったのは街はずれのモーテルを泊まり歩き、土地の人間しか入らないような小さな田舎町のカフェに入ろうとも、ほとんど奇異な目で見られることがなかったことだ……ただし食事はハンバーグやステーキが常食となるのだが(大都市以外ではそれがもっとも間違いない食事だ。よほどのことが無い限り肉のあしらいはさすがに美味い。間違ってもアジア料理は選ばないことである)。
テキサスの終わり辺りから少しづつ風景が変わり始め、ニューメキシコに入ると窓の外の風景は一変する。土は赤く、テーブルのような山があちこちに見える。西部と聞いて日本人が想像する風景が左右に広がる。圧倒的な風景だ。
私はここで一旦北へと進路を変え、サンタフェへと向かった。現在の66はもっと南を一直線に西へと進むが、ここで北へ向かうのは1937年までの古い66のコースだ。
サンタフェは優雅なリゾート地である。スペイン風に赤土の色に壁を塗装たホテルや住宅が並んでいる。ニューメキシコがスペイン領だった名残だ。街中にはインディアン・ジュエリーを商うネイティブアメリカンの露天市も立っている。
一泊一日のつかの間の休息をサンタフェで過ごし、再びルート66を南へ下り、また西へと向かった。
ニューメキコからアリゾナにかけてネイティブアメリカンの居住地区も多い。ルート66周辺はナバホ族とホピ族が住んでいる。ナバホ族の村を探して、私は街道沿いにある一軒のアンティークショップを訪ねた。
「ナバホの村はどこにあるのでしょう?」
「ナバホかい? 外へ出て見なよ。見渡す限りナバホの土地だ」
店から外に出て風景を見直してみた。そこはすべてが居住区だった。後にわかったがルート66から見える風景は居住地区しかないというところもあるほどなのだ。
ニューメキシコ州はその名の通り、カフェで取る食事もメキシコ風のものが多くなってきた。通りすがりに街の食堂に入ると、「よお!!」とネイティブアメリカンらしい男達が私に声を掛けてくる。
「ここの食事はとてもムーチョだ。腹一杯食べていってくれよな」
と。
そして私はニューメキシコから最後の通過州であるアリゾナに入り、今日も昨日と同じようにひたすら走り続けた。
幾つかの街を過ぎ、荒野の中の小さな小さなハックベリーという街に入った時のことだ。一台のクラシックなコルベットを展示してあるカフェが目に入った。車を停めるてみると、カフェと土産物屋を兼ねている建物にはルート66ビジターセンターと書いてある。
すぐに建物の主が姿を見せた。男の名前はジョンと言った。ここで妻のケリーと暮らしているらしかった。
「75年に高速道路が出来てから、ルート66は死んでしまったよ。僕はここに来る前はシアトルに住んで、クラシックカーのコレクターをしていたんだ。二年前にルート66で行われるクラシックのラリーでここに来た。そしてこの街が気に入ったんだよ。66を愛しているし、いろんな人たちと出会えるしね。ここで暮らしたいと言ったら妻もそうしたいと言ってくれた。だからこうしてここにいる」
ジョンはそう語った。
この道には様々人生がある。66の名前にすがって生きている者もいれば、66を守る者もいる。いや……、多分66はそれ自体が人生なのだ。
旅の日々が6日を過ぎた頃のことだ。
「飽きたぁ!!」
ドライバーの木内が叫んだ。当たり前の事だった。少々風景が変わろうが、もはや私たちの刺激になりはしない。壮大で美しい風景もあった。古き良きアメリカを思い起こさせる小さな魅力的な街にも幾つか出会った。しかし今は過ぎゆく街を似た風景にしか感じない。食事はハンバーガーとステーキに、メキシカンが加っただけだ。夕べの宿も、さっき食べた食事も吹き抜ける風のように記憶から去っていく。心の中にあるのは今のことと、次ぎの宿と食事のことだけだ。そしてまるで行のようにひたすらルート66を走り続けた。
コロラド河を越えるとカリフォルニアだ。もう到達点は近い。オールド66はカリフォルニアの砂漠を抜けていく。
旅の終わりが近づくといつの間にか私も、この走り飽いた道のことを『オールド66』と思いを込めて呼ぶようになっていた。
途中の小さな街、ニューベリースプリングには映画の舞台となったバグダッドカフェがあった。映画『バグダッドカフェ』は、どこにも行き場のない女と男が砂漠の中のカフェに愛に満ちた居所を見つけだす物語だった。
オールド66はヨーロッパからの移民たちが辿った道である。彼らは東海岸から中西部のシカゴを拠点にオールド66を辿ってと、ワイルドウエストを過ぎ、西海岸で新しいアメリカの文化を生んだ。その歴史は古ぼけながらもまだオールド66に息づいていた。きっと捨て去った過去を痛みを込めて思い出し、自らの姿を再び取り戻すために、アメリカ人たちはオールド66を辿るのだろう。
私がたどりついLAのサンタモニカフルバードには新しいパーソナルコンピュータの文化が息づく街があった。西海岸を中心に築き上げられたパーソナルコンピュータとネットワークは、アメリカが創り出した新しい時代の文化である。
しかし道の途上にはまだ古ぼけたブルージーンズの下に、がっしりとしたブーツを履き、帽子を被ってよく働く男達と女達がいた。馬をワゴン車で引っ張り、旅をするロデオマンがいた。インディアンジュエリーやアートを商うネイティブアメリカンの姿があった。この道を愛し、見つめ続ける人たちがいた。住み着いて二人で古いコルベットを守って暮らす夫婦がいた。
それこそが海の向こうの日本で私たちが憧れたアメリカの姿だった。
いかに時は過ぎようがが、様々な姿が変わらずにこの広い大陸、そして愛すべき国アメリカには並列に共存している。その懐の広さこそがアメリカなのだと私は思う。
残されたオールド66を味わうように車窓から見つめた。サンタモニカブルバードの向こうにある海岸には眩しく美しい夕日が私を待っている……。到着はアメリカの太平洋時間で午後6時。迷いながら、あるいは行きつ戻りつしながら走り、トリップメーターは走行距離2638マイルを指していた。キロにして4221。シカゴを出て十日後のことだった。海の向こうは日本である。私はもうオールド66を去らねばならないのだ。
夕日の中で、そのことを私は寂しく思っていた。